2024年09月13日
それは「良い経験」ですか?
いきなりですが質問です。
「経験」と「体験」の違いは何だと思いますか?
辞書を引くと、その用法の違いが以下のように説明されています。
———————————————-
日常的な事柄については「経験(体験)してみて分かる」「はじめての経験(体験)」などと相通じて用いられる。
「経験」の方が使われる範囲が広く、「経験を生かす」「人生経験」などと用いる。
「体験」は、その人の行為や実地での見聞に限定して、「恐ろしい体験」「体験入学」「戦争体験」のように、それだけ印象の強い事柄について用いることが多い。
(goo辞書より)
———————————————-
いかがでしょうか。
「まあそうかな」とも思いますが、使いどころ(用法)の違いだけでなく、この2つの言葉の持つニュアンスの違いもありそうです。
「経験を積む」とは言いますが、「体験を積む」とは言わない。ここから「体験は1回限定」というニュアンスもくみ取れます。
そしてもうひとつ。
「体験」は「とにかく実際にやってみること」という意味で使われるのに対し、「経験」は「実際にやってみることで何かを学ぶ」という意味合いが強いと思われます。
そう、私たちの学びの一手段として「経験」はとても重要なのです。
(当たり前すぎとも言えますが)
スポーツでレベルアップするための「実践経験」、仕事のスキルアップをはかる「OJT」などはまさにこの「経験」が成長に重要なことの現れです。
料理や掃除のような家事のスキルもやはり「経験」がものを言います。
しかし、「経験すれば成長できる」という単純なものではありません。
必要なのは経験の「質と量」です。
重要なのは「質」、つまり「良い経験」を重ねることです。
ここで「質より量とも言うのでは?」と思われるかもしれません。
確かにブレーンストーミングでは「質より量」を重視します。たくさんのアイデアを出せば、その中に光るアイデアがある確率が高くなるからであり、単純な確率論です。
しかしブレストに「質より量」が当てはまるのは、それが「アウトプット作業」だからです。
学びという「インプット作業」では、役に立たない経験を繰り返すことは意味が無い…とまでは言わないまでも、少なくとも効率が悪すぎます。
だから経験を積む、つまり「経験の量」も重要なのですが、そこでも「質の高い経験を積む」ことが必要なのです。
ではどうしたら質の高い、つまり「良い経験」が積めるのか。
外部要因、つまり自分が選べないケースでは、「与えられた経験が良いかどうか」でしょう。
たとえば上司から指示された仕事が良い経験になるのか、それともならないのか。確かに自分の成長にとってあまり意味の無い経験をせざるを得ないケースはあります。
しかしここで考えてみてほしいのです。
本当にその経験はあなたの成長にとって意味が無いのでしょうか?
ある仕事を良い経験にするかどうか、それは自分自身にもかかってくるのです。
ゴルフの打ちっぱなしに行くにしても、何も考えずに200球打つのと、自身の課題から意識すべき点を明確にして毎スイングをチェックして100球打つのとでは、後者の方が圧倒的に成長に繋がります。
前者が[5×200=1000]、後者は「20×100=2000」の経験ということです。
この事例からもわかる「良い経験を積む」ポイントは以下です。
1. どんな経験も「良い経験にするには?」を考える
自分のやりたい仕事ではないからといって「つまらない仕事だなあ」と考えるのはもったいないです。たとえば議事録をまとめることを指示されたとき、取るに足らない仕事ととらえてイヤイヤやるのか、あるいは「シンプルに整理し、まとめるトレーニング」ととらえるのか、それによって単なる作業か「良い経験」かは違ってきます。
「言われたからやる」や「イヤイヤやる」のでなく、なにか自分にとってプラスになることはないのか、それをまず考えるのです。
2. 良い経験にするには「何を意識すべきか」を考え、明確化する
「良い経験」にするための方向性が見えてきたら、次に考えるべきは「どうやって?」という具体策です。議事録作成であれば「議論の経過を図にしてみる」とか、ゴルフの打ちっぱなしなら「頭を動かさない」とか、様々な意識すべきポイントが思いつくはずです。
しかしここで注意すべきは、いくつものポイントのなかから「今回意識すべきポイントを絞る」です。なんでもかんでも意識するのは難しい、というか無理です。それではかえって中途半端な経験になりかねません。
だから「今回はこれ」と1つか2つにポイントを絞り込みましょう。それができたら次回に別のポイントを意識すれば良いのです。成長を焦るのは禁物です。
今回はとてもベーシックなテーマですが、このテーマを選んだのにはきっかけがあります。
MCCでは来年度に向けてスタッフ全員が抱負を発表するイベントがあるのですが、そこであるスタッフが「『楽しむ』と『面白がる』の違い」を語りました。
曰く、「『楽しむ』は受動的だが『面白がる』は能動的、だから何でも『面白がる』意識でいきたい」ということでした。
日頃から類義語の違いを意識している私には刺さる発表でした。
そう、「良い経験を積む」ためのもうひとつの、いや最大のポイントは、それを「面白がる」ことだと思うのです。

桑畑 幸博(くわはた・ゆきひろ)
慶應MCCシニアコンサルタント
慶應MCC担当プログラム
ビジネスセンスを磨くマーケティング基礎
デザイン思考のマーケティング
フレームワーク思考
イノベーション思考
理解と共感を生む説明力
大手ITベンダーにてシステムインテグレーションやグループウェアコンサルティング等に携わる。社内プロジェクトでコラボレーション支援の研究を行い、論旨・論点・論脈を図解しながら会議を行う手法「コラジェクタR」を開発。現在は慶應MCCでプログラム企画や講師を務める。
また、ビジネス誌の図解特集におけるコメンテイターや外部セミナーでの講師、シンポジウムにおけるファシリテーター等の活動も積極的に行っている。コンピューター利用教育協議会(CIEC)、日本ファシリテーション協会(FAJ)会員。
主な著書
『屁理屈に負けない! ――悪意ある言葉から身を守る方法』扶桑社
『映画に学ぶ!ヒーローの問題解決力』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2020年
『リーダーのための即断即決! 仕事術』明日香出版社
『「モノの言い方」トレーニングコース』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2017年
『すぐやる、はかどる!超速!!仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2016年
『偉大なリーダーに学ぶ 周りを「巻き込む」仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2015年
『すごい結果を出す人の「巻き込む」技術 なぜ皆があの人に動かされてしまうのか?』大和出版
登録

オススメ! 春のagora講座
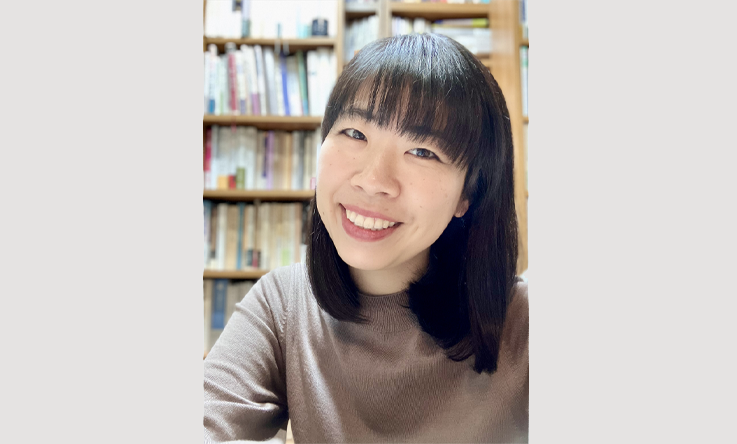
4月27日(日)開講・全5回
神野紗希さんと【俳句】でインストールする「自由」の感性
社会の常識や自意識から解放され、今を軽やかに生き抜く感性を養う創作ワークショップ。

オススメ! 春のagora講座

5月10日(土)開講・全6回
菊澤研宗さんが読み解く【イノベーション論再考:その本質と限界】
主要なイノベーション論の意義と限界を議論し、真に有効なイノベーションの本質を明らかにする。

オススメ! 春のagora講座

6月14日(土)開講・全6回
小泉 悠さんと考える【日本の安全保障】
政治、経済、環境、技術など多角的な要因を考慮する広義な「安全保障」を議論する。
登録





