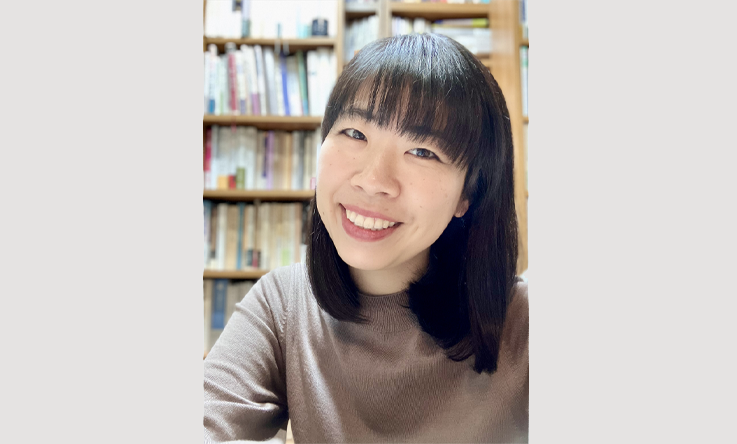ファカルティズ・コラム
2025年02月19日
多様性の功罪
米国トランプ大統領は、先日の航空機事故(米軍ヘリと民間旅客機の衝突)において「バイデン政権の多様性政策が原因だ」とコメントしました。
私も「相変わらずだなあ」と思いましたが、案の定わが国での報道は批判的論調が多いようです。
一部ネットでは賛同する意見もありますが、「悲劇を政争の具にしている」「時代を巻き戻している」「やはり差別主義者」といった意見が目に付きます。
本日はこの「多様性」について考えていきたいと思います。
しかし最初にお断りしておきますが、私は多様性について一般論としても、また今回のトランプ発言についても、ここでその是非を主張するつもりはありません。
最終的にはこれをご覧の皆さんが判断すべきだと思いますので、私はこのテーマについて皆さんが、そしてメディアが多様性の功罪を判断するための「切り口・視点」、言い換えれば「思考の補助線」を提示したいと思います。

私は、多様性については以下の4つの視点で見るべきだと考えています。
————————————————————————-
1. 「人権」の視点
→障害や肌の色などによる差別や偏見の排除を通した平等性・公平性の確保
2. 「政治」の視点
→政党・政治家の支持層である有権者や企業などの有益性
3. 「マネジメント」の視点
→企業・団体の効率的運営やリスクマネジメントのしやすさ
4. 「イノベーション」の視点
→企業・個人・国家が社会に良い変革をもたらす
————————————————————————-
ここからは視座(見る・考える立場)と視野も変えながら、多様性の功罪について考えていきましょう。
まずはトランプ大統領の視座から。
4つの視点の優先順位としては、間違いなく2の「政治」の視点を最優先しています。
重要なのは民主党政権を叩くことであり、彼の支持層の中心である「白人の中高年男性」に「その通り!」と言わせるための発言です。その点では「悲劇を政争の具にしている」という意見は否定できません。
次いで優先しているのは3の「マネジメント」の視点でしょう。「アメリカファースト」を一貫して政治的信条として表明している彼にとって自国経済の成長は必須であり、多様性政策によって自由な採用活動が疎外されてると感じている企業経営者も多いからです。
大統領としてもそうした経営者層を取り込むことも当然考えていますから、その意味ではやはり「政治」の視点もあります。
次に多様性政策によって恩恵を受けていたマイノリティ、具体的には障害者やLGBT、そして黒人・ヒスパニック・アジア系など白人以外の人種の視座で見てみます。
これはもう「人権の視点」一択と言っても良いでしょう。
様々な理由で差別され、就学や就職で冷遇されていた人々にとっては、この政策によって確保される平等性や公平性は生活や自己実現にとって大きな意味を持ちます。
よってこうした人々が今回のトランプ発言を批判するのは当然です。
では、米国の企業経営者の視座ではどうでしょう。
先に述べた「マネジメント」の視点はもちろんですが、それ以上に重要なのが「イノベーション」の視点です。
Googleはなぜ多様性政策が打ち出される前から組織の多様性、つまり様々な人種をはじめとしたマイリノリティを採用していたのか。それはこのイノベーションの視点からです。
均一化された組織、たとえば高学歴の白人男性ばかりの組織では、どうしても同じものの見方や考え方をしてしまう。これでは重要な問題やビジネスチャンスを見落としてしまいがちだし、斬新なアイデアも生まれにくい。
だから組織の多様性を高めなければイノベーションが起こしにくい。Googleをはじめとしたイノベーションを志向する企業が多様性を重視するのは当然なのです。
ここで視野を広げて米国以外、具体的には日本企業の視座でも見てみましょう。
国としてもダイバーシティ経営を推進していることもあり、富士通やソニー、資生堂といったダイバーシティ先進企業は増えています。
しかし「女性管理職を○%に」のような数値目標を達成すればよし、と考える企業もまだまだ多く、成果としてのイノベーションも少ないのが現実です。
これもまた多様性の「罪」と言えるでしょうが、その要因は「公平性(エクイティ)」と包摂性(インクルージョン)の視点の欠如です。
単に組織の多様性(ダイバーシティ)を高めるだけではイノベーションの視点からも、また企業のマネジメントの視点からも意味がありません。
多様な人材に対して公平にチャンスや支援を与えるエクイティと、多様性を活かす仕組みや組織体制というインクルージョンにも同様に取り組むべきです。
この3つの視点を「DE&I(タイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」と呼びますが、このセットなくしてはイノベーションには繋がらないのです。
最後に私たち一般的日本人の視座で「多様性」を見てみましょう。
しかし私たちひとりひとり、モノゴトの見方は異なって当然です。重要なのは、「人権」「政治」「マネジメント」「イノベーション」という4つの視点の「自分なりの優先順位」を明確にすることです。
その上でそれぞれの視点を通した「多様性の功罪」を考えてみる。
このプロセスを経ずに感覚的に、また他人の意見を鵜呑みして「トランプけしからん」とか「多様性なんて必要ない」と語るべきではないと思うのです。

桑畑 幸博(くわはた・ゆきひろ)
慶應MCCシニアコンサルタント
慶應MCC担当プログラム
ビジネスセンスを磨くマーケティング基礎
デザイン思考のマーケティング
フレームワーク思考
イノベーション思考
理解と共感を生む説明力
大手ITベンダーにてシステムインテグレーションやグループウェアコンサルティング等に携わる。社内プロジェクトでコラボレーション支援の研究を行い、論旨・論点・論脈を図解しながら会議を行う手法「コラジェクタ®」を開発。現在は慶應MCCでプログラム企画や講師を務める。
また、ビジネス誌の図解特集におけるコメンテイターや外部セミナーでの講師、シンポジウムにおけるファシリテーター等の活動も積極的に行っている。コンピューター利用教育協議会(CIEC)、日本ファシリテーション協会(FAJ)会員。
主な著書
『屁理屈に負けない! ――悪意ある言葉から身を守る方法』扶桑社
『映画に学ぶ!ヒーローの問題解決力』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2020年
『リーダーのための即断即決! 仕事術』明日香出版社
『「モノの言い方」トレーニングコース』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2017年
『すぐやる、はかどる!超速!!仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2016年
『偉大なリーダーに学ぶ 周りを「巻き込む」仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2015年
『すごい結果を出す人の「巻き込む」技術 なぜ皆があの人に動かされてしまうのか?』大和出版
登録
登録