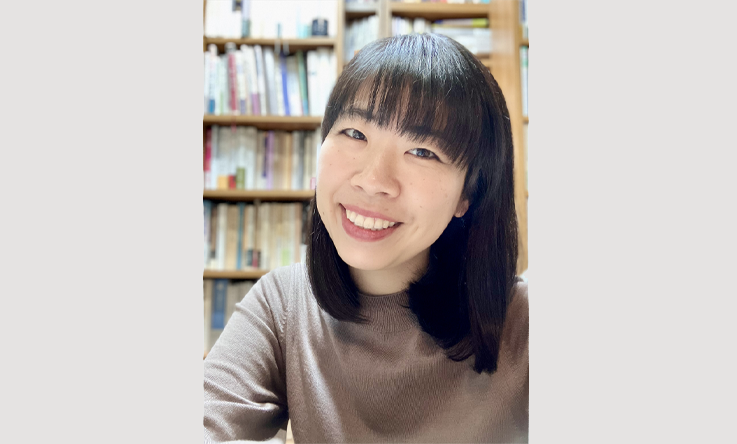ファカルティズ・コラム
2021年09月09日
独創的発想を阻む壁と処方箋
本日のテーマは「なぜ独創的なアイデアを出すのは難しいか」。
「イノベーション」が必要だ、と言われて久しいですが、そこで必要になってくるのは「独創的なアイデア」。
今まで誰も思いつかなかった、というのは難しくとも、「日本企業では」「業界では」「社内では」誰も思いつかなかったようなアイデアが出せなければ、イノベーションなど絵に描いた餅になってしまいます。
また、イノベーションとまで行かなくとも、自社として、またひとりの人材としての「差別化」のためにも、独創的なアイデアを組織として、そして個人として出せるようになりたいものです。
ここでは特に「人材」にフォーカスし、「なぜ独創的なアイデアが発想できないのか」、
そして「ではどうしたら独創的なアイデアが出せるようになるのか」を考えてみたいと思います。

さて、「なぜ独創的なアイデアが発想できないのか」、私はその理由は3つあると考えます。それは『考えることに手を抜いている』から、そして『常識や経験に縛られている』から、さらに『自分ひとりで苦労している』からです。
1.考えることに手を抜いている
人が「うーん」と考えて最初に出てくるアイデアなど、所詮「誰にでも思いつきそうなアイデア」でしかありません。
もちろん最初から独創的なアイデアを思いつく場合もあるでしょうが、それは偶々であり、毎回毎回アイデアを出そうとする度にすぐに独創的なアイデアが出せる人などいないでしょう。
それにも関わらず、ちょっと考えて出てきたアイデアに「これ、いけるんじゃないか?」と飛びついてしまう。あるいは何個かアイデアが出たところで「まあ、こんなもんだろう」と考えるのを止めてしまう。
これははっきり言って「手抜き」です。
重要なのはアイデアの「量」なのです。
コピーライターやデザイナーなど、所謂クリエイターと呼ばれる人たちは七転八倒しながら大量のアイデアを出し、その中でひとつでも当た
ればラッキー、という考えで頑張っています。
ブレーンストーミングの鉄則のひとつに「質より量」があるのもそのためです。宝くじを買うのに1枚しか買わないのと100枚買うのと、どちらが当たりが期待できるか、それと同じ『確率論』の問題です。
だからまず考える前に「出すアイデアの数と所要時間」を決めましょう。1時間で100個とか、とにかく必死に、しかしタイムトライアルのゲームをしているつもりで、楽しみながら大量にアイデアを出すのです。
2.常識や経験に縛られている
ブレストの鉄則の2つめに「自由奔放」があります。「これは金かかりすぎてダメだろうなあ」など、コストや技術的難易度、法律など、アイデアの実現を阻む様々な「制約条件」があるのは事実ですが、それを気にしていたら独創的なアイデアなど出ません。
しかしいくら上司から「今回は制約ゼロで考えよう!」と言われても、独創的なアイデアがなかなか出ないのも現実。これは私たちが「無意識的に今までの常識や経験に縛られている」からです。無意識ですからどうしようもありません。
その対処法のひとつが『アナロジー(類推)』で考えるのが有効です。特に本ブログでも何度か取り上げている「メタファー」を用いたアナロジーがオススメです。
たとえば新店舗の企画を考えるとき、神社仏閣のメタファーで考えてみる。まずは神社仏閣の「あるある」を考える。そうすると「ご神木」や「手水場ヶ、「おみくじ」や「参道の出店」が出てきますから、次にこれら「あるある」が人事や仏閣において何を意味するのかを考え、それを強引に自社の新店舗に応用する。そうすると今まで思いつかなかったアイデアが出てきやすくなります。
重要なのが、このプロセスが「一度本来のテーマから離れる」ことを可能にするということ。これによって自社や業界の常識や経験からも離れて、今までは出せなかったアイデアを出せる可能性が上がるわけです。
眼鏡屋さんのJINSがユニクロやスウォッチという他業界のメタファーから自社のビジネスモデルを構築し、成功したのも同じで、やはり「一度本来のテーマから離れる」のは有効です。
3.自分ひとりで苦労している
確かに天才はいます。しかし私たちは他者と協働することで天才を超えることができる。それが「三人寄れば文殊の知恵」であり、「コラボレーション」と呼ばれるものです。
誰かのアイデアを「面白い」と感じ、それをちょっと捻って「だったらこういうのは?」と新たなアイデアを思いつく。これが『触発』であり、触発の連鎖が思いも寄らぬ独創的なアイデアに繋がります。
だからどんどん他者のアイデアを改造/改良し、さらに組み合わせて別のアイデアにしてしまえばいいのです。自分ひとりで苦労する必要などどこにもありません。ブレストの鉄則の3つ目「改善・結合歓迎」はまさにそれです。
そのためにも重要なのがブレストの鉄則のラスト「批判厳禁」です。いかに他者のアイデアに「つまんない」「ムリだろ」と感じたとしても、決して否定せずに一度は「イイネ!」と言ってみる。そこから改造や組み合わせをすればいいのです。また否定された方もやる気を無くしてしまいますので、それではコラボーレーションになりませんから。
ただ、「否定」はダメですが「疑問」は持っても構いません。というか積極的に他者のアイデアに疑問を持ちましょう。「なるほど、確かにそうしたニーズはありそうだ。でもコロナ禍においては真逆のニーズもあるんじゃなかろうか? とすると…」といったように、疑問から新たなアイデアが生まれることもあるからです。
ブレストに限らず、否定ばかりでは仕方ありませんが、議論において「ですよね」「それでいいと思います」と単に同調が連鎖・伝搬していくのは日本の会議の悪しき文化だと私は考えています。
先に述べた「常識や経験に縛られない」ためにも、もっと「積極的に疑問を持つ」必要があると考えますし、イノベーションもそこがキモになるのではないでしょうか。
今回は私の専門でもある「イノベーション」という視点で「なぜ独創的なアイデアを出すのは難しいか」というテーマでその原因と処方箋を考えてみました。
少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
登録
登録