夕学レポート
2010年11月27日
ポピュラーミュージックのイノベーター 菊地成孔さん
芸術やスポーツが、大衆エンタテイメントとして成立するためには、条件がある。
ズブの素人からその道のプロまで、幅広いファンを抱え、それぞれに異なった楽しみ方が存在することである。
例えばサッカーであれば、ルールが分からない人でも、贔屓チームの勝ち負けや人気選手のプレーに一喜一憂できる。一方で、サッカー経験者やオタク的ファンは、監督の采配や戦術、選手の技術論についてウンチクを開陳し合って楽しむ。選手・コーチ同士や職業評論家は、隠されたプロフェッショナリズムを忖度しようとするだろう。
それぞれの人が、各々の鑑賞リテラシーレベルに応じて、自分なりの楽しみ方を味わえる。それが、エンタテイメントとしての深みにつながる。
菊地成孔氏の問題意識は、自身のホームグランドであるポピュラーミュージックの世界には、「リテラシーレベルに応じた多様な鑑賞スタイルがない」ということである。
特に、音楽をたしなむ実践者やコアなファン層の間に、ポピュラーミュージックの技術論や構成テクニックに目を向けて、分析的に鑑賞するという習慣がないということだ。
彼の造語表現を借りれば「ポップアナリーゼ」という鑑賞メソッドの欠落である。
大衆エンタテイメントのど真ん中にあるポピュラーミュージックにおいて、あってしかるべき「ポップアナリーゼ」(実際に西欧社会には存在するという)が、なぜ日本の音楽シーンに根付かないのか。
菊地氏は、音楽理論史のフレームワークを使った壮大なる仮説を示しながら、その理由に迫る。
菊地氏によれば、世界の音楽史には、3つのクオンタムチェンジがあったという。
ひとつは、6世紀から7世紀に起きた「グレゴリオ聖歌」の登場であった。「グレゴリオ聖歌」とは、ローマ・カトリック教会で用いられる、単旋律、無伴奏の宗教音楽である。
従来は口伝によって伝承されてきた音楽に、この時初めてネクマと呼ばれる「楽譜」が付けられたのだ。
「楽譜」を標準装備した宗教歌は、キリスト教伝播促進装置として機能し、西欧社会を席捲していった。
二回目は、18世紀末にフランス人 ジャン=フィリップ・ラモーが著した「和声論」の出現だったという。
近代音楽理論の基礎原理ともいうべき「和声論」によって、科学としての音楽が確立し、音楽は「脱宗教化」をはたし、クラシック音楽として西欧近代知識人の教養に発展していった。
三度目は、1953年米国ボストンに誕生した「バークリー音楽院」であった。
「ポピュラーミュージックを体系的に教える」という世界初の音楽学校の登場である。
ここでは、社会の底辺で発生した野性的な音楽であるブルースやジャズを、クラシック音楽理論のフレームを使って構造化するという授業が展開された。
「ポップアナリーゼ」そのものである。
バークリー音楽院は、世界のポピュラーミュージック業界を支える専門家育成機関の役割も果たした。
バークリーで、「ポップアナリーゼ」に習熟した音楽人は、世界に広がり、ポップスという一大音楽産業を形成していったのだ。
こうして、モータリゼーションやファーストフードのように、ブルースやジャズ、その影響を受けたポピュラーミュージックは、アメリカ発文化の代表として世界に拡大していった。
音楽が、「力と金の論理」に支配される時代の到来でもあった。
さて、日本に、なぜ「ポップアナリーゼ」が根付かなかったのか。
菊地氏は、その理由を、「力と金の論理」に対する、日本人の本能的な拒否感にあったのではないかという。
預貯金は大好きなのに、資産運用や利殖行為には冷ややかな視線を向ける。
ものづくり資本主義の優等生なのに、マネー資本主義にはなじめない。
日本の中間層が、「力と金の論理」の匂いを放つものに対して抱く拒否反応と同じ意識が、米国発のポピュラーミュージックに対しても働いているのではないか。
だから、ポピュラーミュージックを一段低いものとみなし、知識や理論をつかって分析的に楽しむという知的行為になじまないものとする。
これが、菊地氏の仮説である。
当然ながら、仮説の裏側には、「ポップアナリーゼ」をもっと楽しもうよ!という思いがある。
世界の音楽史が、三度のクオンタムチェンジを通して、音楽の意味づけを変えてきたように、日本のポピュラーミュージックの鑑賞法にも、イノベーションがあっていいのではないかという提言であろう。
菊地氏が披露してくれた「ポップアナリーゼ」実践講義は、時間の制約もあって、本質に迫るまでには至らなかった。しかし、日本のポピュラーミュージックにブレークスルーを起こしたいという心意気は、よくわかった。
変革はいつも、辺境から生まれるのだから。
追記:
この講演には8件の「明日への一言」が寄せられています。
http://sekigaku.jimdo.com/みんなの-明日への一言-ギャラリー/11月26日-菊地-成孔/
登録

オススメ! 春のagora講座

6月14日(土)開講・全6回
小泉 悠さんと考える
【日本の安全保障】
政治、経済、環境、技術など多角的な要因を考慮する広義な「安全保障」を議論する。
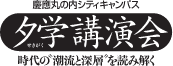
人気の夕学講演紹介

2025年5月27日(火)18:30-20:30
アテンション・エコノミーのジレンマ
山本 龍彦
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)副所長、慶應義塾大学 X Dignityセンター共同代表
偽・誤情報や誹謗中傷、さらには社会的分断の一因になっているとも言われる「アテンション・エコノミー」が孕むジレンマに人権や民主主義の観点から迫り、克服の糸口を考えます。

人気の夕学講演紹介
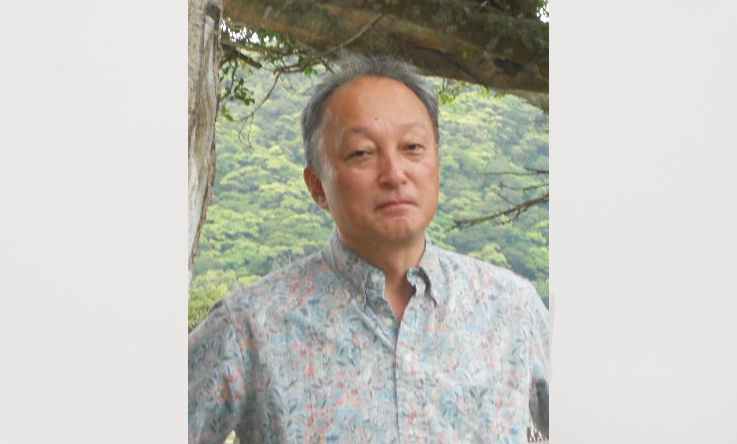
2025年5月30日(金)18:30-20:30
蔦屋重三郎の仕事に迫る
鈴木 俊幸
中央大学文学部教授
NHK大河ドラマ『べらぼう』時代考証教授
次々と流行を生みだしていった蔦屋重三郎との仕事ぶりを辿り、江戸時代中期から後期へと大きく変化する時代の様相を見てみます。
登録




