夕学レポート
2016年04月25日
チャラ男とチャラ子の交流会から生まれるイノベーション|入山章栄先生
 早稲田大学ビジネススクールの入山章栄先生の講演をお聞きした。講演では、ビジネスのイノベーションを生み出す取り組みと、日本企業を支えるアクターとしての個人はどのように立ち振る舞えばよいのかを、海外で主流となっている経営学の理論を紐解きながら教えてくださった。
早稲田大学ビジネススクールの入山章栄先生の講演をお聞きした。講演では、ビジネスのイノベーションを生み出す取り組みと、日本企業を支えるアクターとしての個人はどのように立ち振る舞えばよいのかを、海外で主流となっている経営学の理論を紐解きながら教えてくださった。
イノベーティブなビジネスの創出に求められるのは、「知の探索」(異業種や他分野の知識を活用、参照して知識の幅を広げること)と「知の深化」(異分野の知識を踏まえた部署内での議論やビジネスの作り込み)の両輪である。しかし、実際は「知の探索」よりも「知の深化」に偏りがちになってしまう。知の探索はコストも時間もかかり、かつ成功確率も不明となると、目の前の儲かる事業に力点が置かれがちになるのは誰もが理解できることである。
そこで、「知の探索」を促すために個人レベルで取り組めること。それは社会的な人と人のつながる、つまりは人脈だ。それも、「強い人脈(親友レベル)」ではなく「弱い人脈(知り合いレベル)」の方がクリエイティビティに貢献することが社会学の見知から明らかになっている。
とりあえず名刺交換をして、メールのやりとりができるくらいの弱い結びつきをたくさん作れるような人を、入山先生は「チャラ男とチャラ子の異業種交流会」に例えて解説してくれた。異業種交流会に積極的に参加して名刺を集めている、「チャラ男」「チャラ子」と呼ばれるタイプの人は、さまざまな情報の持ち主との弱いネットワークにより思わぬアイデアを持っている事があるというのだ。
 さらに、海外の理論では、情報の持ち主同士を結びつける役割(ネットワーク理論におけるストラクチャル・ホールがある位置)に自分を位置づけ、情報集積地点となることで、いつでも必要なときに、効率よく情報が収集できるという。商社などはまさにこの立ち位置にいる。
さらに、海外の理論では、情報の持ち主同士を結びつける役割(ネットワーク理論におけるストラクチャル・ホールがある位置)に自分を位置づけ、情報集積地点となることで、いつでも必要なときに、効率よく情報が収集できるという。商社などはまさにこの立ち位置にいる。
しかし、ストラクチャル・ホールを個人がいつまでも保持していくことは難しいのではないかとも思う。チャラ男とチャラ子は自らがネットワークを拡散しつづけると、いずれ世界中のゆるいネットワークはストラクチャル・ホールのない状態に陥りはしないだろうか。
異業種交流会で知り合った異分野の人をフェイスブックで検索してみると、意外にも共通の知人がいたことに驚く経験をしたことがある人は私だけではないと思う。「えっ、この間異業種交流会で知り合ったAクンは、Bクンと大学の同期だったんだ、知らなかった!」みたいな。 これで、Bクンのストラクチャル・ホールは「私」との関係において消滅する。
個人のストラクチャル・ホールの大きさには常に差異があるけれど、チャラ子の友達は往々にしてチャラ男であることが多く、また「意識高い系」コミュニティーは拡散し、あるところで合流し続けているのではないだろうか。
ならば、「大勢で考える」というシンプルな方法で、個人の経験や知識を越えた領域に挑戦するのはどうだろう。私の経験では、大勢で考えたほうがより突飛でイノベーティブなアイデアが思いつくからである。「知の探索」と社内の「知の深化」の間を橋渡しするための
Aクン+Bクン+私の飲み会=「知の交流」
がイノベーションの創出にはあってよいのではないか。
確かにBクンのストラクチャル・ホールは小さくなるけれど、Bクンがイノベーションを創出したいとき、「私」のみならずAクンもその場に呼びだすことができれば、そのうちの二者で考えるより、多角的かつ新鮮なアイデアが思い浮かぶように思う。Bクンのストラクチャル・ホールは消滅したけれど、イノベーションを起こしやすい環境に近づけるのではないか。
ネットワークの話をぼんやり考えていて、真っ先に思い浮かんだのが慶應義塾大学の同窓会「三田会」のことである。塾員としては、これほど居心地がよくて困ったときに役に立つ組織はないのだが、それは同質的な仲間が集まっているからである。たまには、稲門会と本気でイノベーティブなビジネスについて考えてみる飲み会もありかもしれない。
登録

オススメ! 春のagora講座
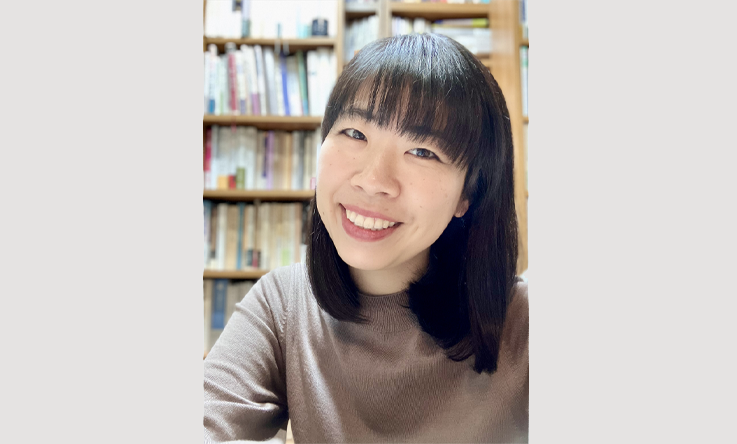
4月27日(日)開講・全5回
神野紗希さんと【俳句】でインストールする「自由」の感性
社会の常識や自意識から解放され、今を軽やかに生き抜く感性を養う創作ワークショップ。

オススメ! 春のagora講座

5月10日(土)開講・全6回
菊澤研宗さんが読み解く【イノベーション論再考:その本質と限界】
主要なイノベーション論の意義と限界を議論し、真に有効なイノベーションの本質を明らかにする。

オススメ! 春のagora講座

6月14日(土)開講・全6回
小泉 悠さんと考える【日本の安全保障】
政治、経済、環境、技術など多角的な要因を考慮する広義な「安全保障」を議論する。
登録




