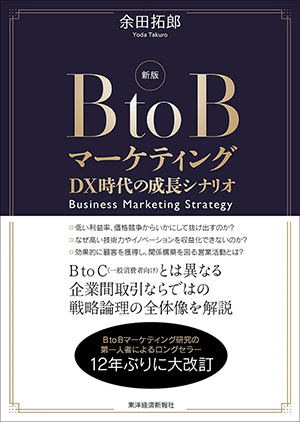ピックアップレポート
2023年12月12日
余田 拓郎『新版 BtoBマーケティング―DX時代の成長シナリオ―』
これまでマーケティングは、消費財がその中心にあった。近年、この状況は変わりつつある。購買のグローバル化や電子商取引の拡大によって、部品や素材、あるいは設備、サービスなどの法人向けマーケティングへの関心が高まってきた。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展とともに、新規顧客の開拓や既存顧客との関係強化のあり方が大きく変化したことも、BtoB(Business to Business)領域におけるマーケティングへの関心を高める要因の1つとなっている。
技術革新の進展に伴う部品・工程の変更や顧客企業の系列取引の見直しが進み、新規顧客の獲得や関係性構築が重要性を増している。またグローバル市場への進出は、新たな顧客の取り込みが避けては通れない状況をもたらしている。一方、インターネットの普及や電子商取引の拡大に伴い、新規顧客の獲得機会が増している。ネットを活用した既存顧客へのアプローチも、営業人材の不足と相まって企業成長のための喫緊の課題となっている。このような環境変化の中で、新規顧客の開拓や既存顧客との関係強化を効率的に進めるために、法人向けマーケティングの積極的展開が求められている。
近年、BtoBの領域で拡大しているインサイドセールスやウェブマーケティングも、こうした環境変化に対処するための新たな取組みである。顧客の獲得や関係構築において、従来どおりの人的な営業活動にのみ依存したやり方だけでは効率が悪くなってきた。法人向けの営業活動でも、消費財で行われてきたような購買プロセスを理解しつつ、ステージごとに適切な対顧客活動、つまりマーケティングを展開しなければ、効率的に顧客を獲得して維持することは難しい。
どの部門のどの階層の人がどのような権限を持って意思決定にかかわっているのか、案件や取引先、購買ステージごとにその特質を検討し、適切な施策が行われなければ、営業活動もきわめて効率の悪いものとなる。従来の営業活動ではカバーしにくい領域が拡大する中で、法人向け営業の領域でも組織的なマーケティングへの転換が求められるようになっている。
本書は、日本BtoB企業の持続的成長に向けた対市場戦略を考える書である。P・F・ドラッカーは、The Practicesof Management (『新訳 現代の経営』上田惇生訳、ダイヤモンド社)の中で、企業の成長に欠かせないのは「イノベーション」と「マーケティング」だと指摘した。すでに半世紀以上も前の著作になるが、日本のBtoB企業についていえば、ほとんどが「イノベーション」に注力するものの、「マーケティング」は蚊帳の外に置かれたままである。その結果、イノベーションを収益化することに失敗している企業がきわめて多い。
対市場活動としてのマーケティングの欠落は、さまざまなところで見ることができる。たとえば、プライシング(価格づけ、見積り)である。日本のBtoB企業の多くが製造原価にいくらかの利益を上乗せして、価格をつけている。しかし、マーケティングのテキストを見れば、価格は、(1)原価の積み上げ、(2)競合の値づけ、(3)顧客のWTP(Willingness To Pay:支払意思額)を総合的に勘案して決めるべきであると書いてある。実際には日本のBtoB企業の多くが、(1)の原価にばかり注目している。
もし、顧客ニーズが本当に重要だというのならば、顧客の求める価格/品質関係に十分配慮したうえで、見積りを作成すべきだろう。その際には、品質や製造工程も見直さなければならないかもしれない。また、場合によっては、機能を省略することも必要になるだろう。しかし、顧客ニーズが重要だということが頭でわかっていても、実際の行動では、原価や利益という自社の都合によって価格が決められている。
このような傾向は、プライシングに限らない。自社の都合にしか目を向けない戦略展開が多く行われている。これをここでは「行き過ぎたシーズ志向」と呼ぶことにしよう。行き過ぎたシーズ志向は、プライシングに限らず、開発できた製品を売る、利用できる代理店を通じて販売する、捻出可能な前年並みの予算で広告を打つ、などのさまざまな場面で見ることができる。日本の多くのBtoB企業は自社の都合を優先させて、顧客に製品を提供しているといってよいだろう。つまり、対市場活動としてのマーケティングが軽視されているといえる。
日本企業の売上高利益率は、この半世紀にわたりほぼ一貫して低下してきた。特に利益率の低下が顕著なのは製造業であり、なかでも素材や部品、設備といったBtoB企業の利益率の低下傾向は著しいものがある。行き過ぎたシーズ志向の結果、持続的成長の源泉となる利益にしわ寄せが生じているのである。
一方、日本の技術力はというと、いまだ優位に立つ業界が数多く存在する。半導体の製造にかかわる装置や炭素繊維、電池関連素材など世界をリードしている産業財も少なくない。日本企業のプレゼンスは世界においていまだ高いものがあり、上述の利益率の低下と符合しない。
現在、日本のBtoB企業が抱える課題は、技術の高さが利益に結びつかないところにある。取引は、価格に見合う製品だから成立するのである。利益を生まないということは、言い換えれば、顧客が低い価値としか認めていないからである。マーケティングの用語でいえばWTPが低いということになる。
WTPの低さは、さまざまな形で企業の成長に影響する。再投資のための資金に差を生むし、従業員に分配することのできる給与にも差を生む。それは、さらには優秀な人材の獲得にも影響を及ぼす。また、企業の時価総額にも影響することになり、これによってグローバル市場での戦略への制約や意図せざる離脱を生むことにもなる。
こうした課題はグローバル企業に限らない。収益性の低さは中小企業でより顕著だ。人材に限りがある企業こそ、マーケティングが重要だという認識を持つことである。営業人材に多くの経営資源を割ける大企業なら、人海戦術で顧客開拓や顧客囲い込みができる。中小企業ではそうはいかないところが、中小企業経営者の多くは、企画や調査・分析などの間接部門は、コストセンターとしてできる限り人員を絞り込もうとするようだ。現代の環境は、変化が激しく、それに戦略を合わせることが生き残るための必須条件だ。いくら競合他社より優れた営業力を有していても、向かう方向が間違っていれば、生き残りはおぼつかない。
特定のカテゴリーでトップシェアを誇る日本企業は数多く存在するが、海外企業と比べると利益率は必ずしも高くない。このことは、いくら高い技術を有していても、売り方次第で価格だけが競争軸となりうる、つまり、レッドオーシャンに陥りうることを示している。技術力あってのマーケティングである。他社と差別化された製品がある、他社にはできない高品質な製品やサービスが提供できる、そういった企業こそ売る相手は誰でもよいわけではなく、むしろ積極的に探してくるべきだ。つまり、マーケティングを展開し、自社の部品や素材に付加価値を認めてくれる潜在顧客を見つけてくることによって、自社開発技術が生かされることになる。
本書のねらいは、部品や素材あるいは設備、システムなどの産業財を扱う企業の対市場戦略、つまりマーケティングを考えるところにある。イノベーションや高い技術力を成長に結びつける手段としてのマーケティングに注目するものである。
企業の成長は技術力だけでもたらされるものではない。技術以外の、とりわけ顧客や市場との関連の中で決めるべき戦略が、将来の成長に大きく影響することになる。日本のメーカーの競争優位は、確かに技術力だったのだが、それが今後も続くという保証はない。技術力は成長の必要条件だが、十分条件ではない。技術力を企業の成長にどのようにして結びつけるかが日本の経営者に問われている。
ドラッカーは、上述の著書で、「マーケティングの重要性を完全に理解できるようになるためには、販売を卑しい寄生的なものと見、生産を紳士的なものと見る社会的な偏見、およびそのような見方の結果としての生産を事業の決定的な機能とする間違った理論を超克しなければならない」と続けている。このドラッカーの指摘する「販売を卑しい寄生的なものと見」ることを止めない限り、日本の製造業がグローバル市場での勝者となることはないだろう。
本書は、前作と位置づけられる『BtoBマーケティング―日本企業のための成長シナリオ』を大幅に加筆修正したものである。前作を出版し10年以上経過したことから、インターネットの浸透やインサイドセールスの普及など、近年の環境変化を踏まえて加筆した。
『新版 BtoBマーケティング―DX時代の成長シナリオ―』(2023)の「序章」を著者・出版社の許可を得て抜粋・編集しました。無断転載を禁じます。
【こちらの記事もおすすめ】
余田拓郎『BtoBマーケティング―日本企業のための成長シナリオ』(2011)

余田 拓郎(よだ・たくろう)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授
慶應義塾大学ビジネス・スクール 教授
慶應MCC担当プログラム
ビジネスプロフェッショナルのマーケティング戦略
BtoBマーケティング
1984年 東京大学工学部電気工学科卒業。住友電気工業株式会社を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了(MBA)、同大学大学院経営管理研究科後期博士課程修了。経営学博士。1998年名古屋市立大学経済学部専任講師。同助教授を経て、2002年より慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授。2007年4月より同教授。
登録
登録