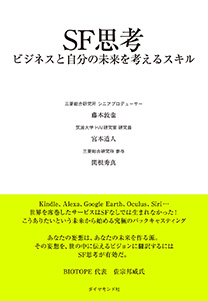今月の1冊
2025年04月08日
『SF思考 ビジネスと自分の未来を考えるスキル』
皆さんの好きなSF作品はなんですか?
映画でもアニメでも、また舞台や小説でも結構です。
情報誌Time Outロンドン版の調査によると、SF映画のベスト10は以下の通りとなっています。
1.「2001年宇宙の旅」(1968)
2.「ブレードランナー」(1982)
3.「エイリアン」(1979)
4.「未知との遭遇」(1977)
5.「エイリアン2」(1986)
6.「スター・ウォーズ」(1977)
7.「未来世紀ブラジル」(1985)
8.「メトロポリス(1926)」
9.「ターミネーター」(1984)
10.「スター・ウォーズ 帝国の逆襲」(1980)
スター・ウォーズとエイリアンシリーズから2作ランクインしてますね。
個人的には上記ランキングには入っていませんが、アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」や古き良き東宝特撮「妖星ゴラス」、そして海上自衛隊と米海軍が協力して異星人に立ち向かう「バトルシップ」なども好みのSFです。
また、中高生の時には「日本沈没」の小松左京、「時をかける少女」の筒井康隆、ショートショーの星新一など、様々なSF小説を読んでいました。
ところで今さらではありますが「SF」とは何でしょうか。
文字通り「Science Fiction」、科学的な空想に基づいた空想のことで「空想科学小説」とも訳されます。
つまり「科学的であること」がSFの要件です。「ハリー・ポッター」や「ロード・オブ・ザ・リング」といった「剣と魔法とドラゴンの世界」を描いた作品はSFでなく「ファンタジー」と呼ばれるジャンルなのです。
※このあたりの定義は様々な説と論争があるので、これ以上は避けます。
前置きが長くなりました。
この「SF」、というより「SF的な発想をもとに、よりよき未来を創るための戦略を立てよう」と訴えるのが、今回ご紹介する「SF思考」です。
少し考えてみてください。
先に挙げた数々のSF作品にはどのような共通点がありますか。
はい、宇宙を舞台にした(あるいは異星人が登場する)作品が多いですね。
ちなみにアポロ11号による月着陸より7年前に、宇宙飛行士が当たり前になった時代が「妖星ゴラス」には描かれています。
そして「ブレードランナー」「未来世紀ブラジル」「メトロポリス」「ターミネーター」、そして「PSYCHO-PASS サイコパス」は未来社会、特にディストピアが舞台になっています。
コンピューターやAI、そしてアンドロイドに支配される未来。「PSYCHO-PASS サイコパス」では、人間のあらゆる心理状態や性格傾向が計測・数値化され、それによって職業が決められたり、犯罪者予備軍として処分すらされてしまう未来の日本が描かれています。
そしてもうひとつの共通点。
それはこれらSF作品が「予言の書」であるという点です。
いや「予言の書」とは適切な表現ではありません。正確には「SF作品に描かれた未来社会やガジェットが実現しつつある」という事実です。
「スター・ウォーズ」の序盤、主人公のルークはC-3PO、R2-D2という意志を持ったロボットと出会い、レイア姫からのメッセージを受け取ります。そのメッセージは空中に投影されたホログラムでした。
ご存じの通りロボットはAIによって自律性を持ち始めています。「ターミネーター」ではそれが未来からの暗殺者として登場し、「2001年宇宙の旅」ではコンピューター「HAL」が搭乗員を殺害します。
現在、まさにAIのシンギュラリティについて議論されています。そこに「ターミネーターのような未来にならないために」という危機感が背景にあるのは明らかです。
また、3次元映像のホログラムもそれに近いものがコンサートやVRによって実現しつつありますし、「スター・ウォーズ」に登場する「空中キーボード」も…
こうした「SF作品に登場する社会やガジェットの実現を目指して、まずはそれに近いもの、実質的に同じ機能を持ったものを作ろう」というのが、本書で紹介されている「SFプロトタイピンク」という手法です。
私が慶應MCCと企業研修で行う「イノベーション思考」でも取り入れている手法ですが、概ね以下の手順で行います。
1. 情報収集
シンクタンクや研究機関、省庁などが公開しているマクロトレンド情報や、各種技術ロードマップなどを広く集め、読み込みます。
2. 未来ストーリーづくり
集めた情報を元に「ありたい未来」を描きます。「30年後の旅行」や「50年後のモビリティ」など、ジャンルを決めて考えます。
最初は「○○が××によって△△になっている」といった箇条書きでも構いませんが、それでは解像度が低くイメージしにくくなります。
作りたいのは「ストーリー」ですから、そのためには登場人物が必要です。
主人公やその家族、恋人に敵役や師匠のような存在など、セリフも入れながらSF作家になったつもりで、また様々な夢想をしていた幼い頃の自分に戻って、自由に「妄想」しましょう。
ひとつのコツは「具体的な人物設定」です。年齢や性別、経歴や家族構成に趣味など、この人物設定をしっかりやると、架空の登場人物が「勝手に動き、話す」ようになります。漫画家さんなどもよく使う手法です。マーケティングで顧客の「ペルソナ」を描くのも同じですね。
本書ではサンプルとしてプロのSF作家も協力したストーリーが紹介されており、それを読むだけでもワクワクできます。
3. 未来に向けたコンセプト
「ありたい未来」が描けたら、自社のビジネスに立ち返ります。
「30年後の旅行がそうなっているためには、20年後はどこまで実現できている必要があるのか、そして10年後には、だとすると今やるべきことは?」のように、未来から現在に時間を巻き戻していきます。
これが現状から未来を読む「フォアキャスト」の反対の「バックキャスト」と呼ばれる手法です。
この過程で未来のガジェットの現実解なども見えてくるわけですね。
ここでは自社の長期戦略への応用についてお話ししましたが、本書では作成したSFストーリーの活用例についてもいくつも紹介されています。
では、最後にSFプロトタイピングの練習で締めましょう。
我が国の誇るSFである「ドラえもん」。様々な「ひみつ道具」でのび太君を助けてきましたが、あなたならどのひみつ道具がほしいですか。
そしてそのひみつ道具を現在、あるいは近未来の技術で実現するとしたら、どのようなガジェットや仕組みになりますか。それを考えてみてください。
たとえば…
誰でもほしい「どこでもドア」。要するに「移動時間をゼロにする」のがこの道具ですから、実質的に同じものを作ろうとすると、移動時間を感じさせなければ良いわけです。
ということで私が考えたのが「睡眠ポッドによる海外旅行」。
成田空港で搭乗手続きをしたら、各自用意された睡眠ポッド(言い方は悪いですが棺桶っぽいもの)に入り、睡眠ガスで眠りにつきます。
その何百というポッドを旅客機(というより貨物機?)に積み込んで出発し、目的地に着いたら覚醒させる。座席も食事も不要なので低価格で実現できます。
目が覚めたら目的地。移動時間を「感じない」ので、「実質どこでもドア」です。
もちろん法的、倫理的な問題はありますが、それを気にしていたらイノベーションなど起こせません。まずはそれら阻害要因に目を瞑り、ゼロベースで「妄想」することが重要です。
さあ、あなたならどの「ひみつ道具」のプロトタイプを妄想しますか?
(桑畑 幸博)
◆宮本 道人氏講演◆
「SF思考が切り拓く未来:「もしも」を考えてVUCA時代を生き抜く」

宮本 道人(虚構学者、応用小説家、SF思考コンサルタント)
6月4日(水) 18:30-20:30(見逃し配信あり)
→丸の内会場の受講はこちら
→オンライン受講はこちら
登録

オススメ! 春のagora講座

5月10日(土)開講・全6回
菊澤研宗さんが読み解く【イノベーション論再考:その本質と限界】
主要なイノベーション論の意義と限界を議論し、真に有効なイノベーションの本質を明らかにする。

オススメ! 春のagora講座
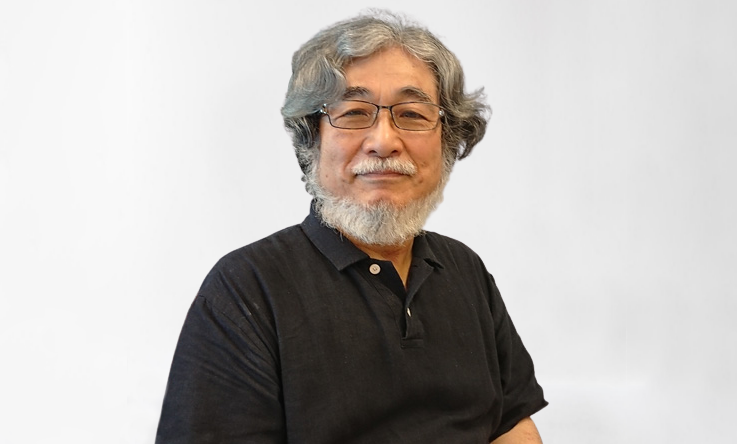
5月17日(土)開講・全6回
平野 昭さんと【系譜で読み解くクラシック音楽】
近年再評価や再解釈の進むブラームス音楽の本質と、ドイツ・ロマン派音楽の豊かな魅力を楽しむ。

オススメ! 春のagora講座

6月14日(土)開講・全6回
小泉 悠さんと考える【日本の安全保障】
政治、経済、環境、技術など多角的な要因を考慮する広義な「安全保障」を議論する。
登録